企業防衛で
経営者の万一に備える
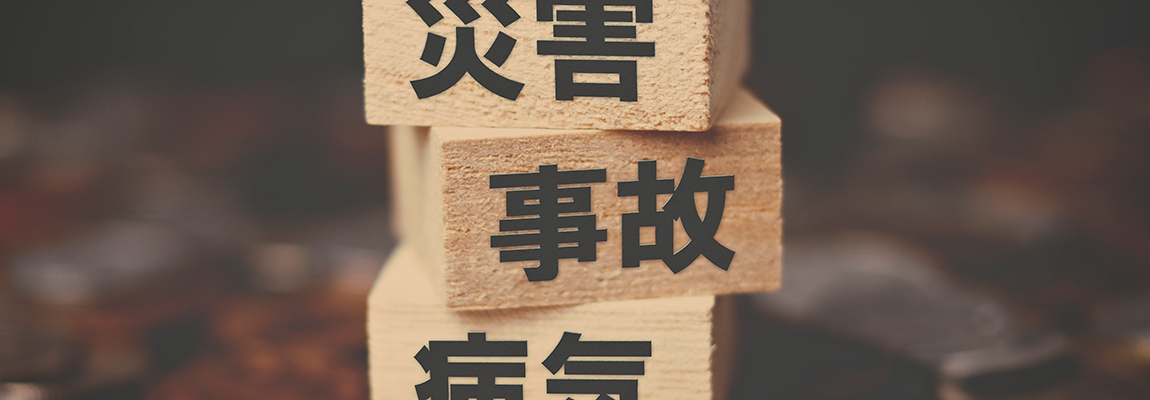
なぜ会計事務所が保険指導をするのか?
私たちTKC会計人の理念には
- 関与先の永続的発展
- 関与先完全防衛の実現
を願うという精神が根底にあります。
関与先が不慮の事故や災害に遭遇すると企業は崩壊し、従業員や家族は一瞬にして路頭に迷うことになりかねません。
これらのリスクから企業を守るには、いろいろな方法がありますが、その中の一つに生命保険の活用が考えられます。
会計事務所は税務会計を通じ、企業の経営内容などの実情を把握しており、保険加入の目的や適切な保険契約について客観的・中立的に判断できる立場にあります。
その点から会計事務所だからこそ企業のリスクを管理し、生命保険の活用をアドバイスできます。
具体的には標準保障額を算定し、アドバイスを致します。
標準保障額とは
標準保障額とは、企業経営者に不測の事態が生じたとき、その企業が被る経済的損失額を算定したものです。
ここで言う経済的損失額は、
- 経営者の死亡
- 就業障がいおよび重大疾病時
において、その企業が存続(あるいは清算)するためにはどの程度の資金が必要となるかを「運転資金・固定費・借入金返済資金等の社内留保金額」と「経営者本人もしくはご家族に対して支払われる役員退職慰労金・弔慰金の社外支出金」から算定します。
端的に表現すると、
- 企業防衛準備資金(社内留保)
- 役員退職金慰労金準備資金(社外支出)
で算定します。よって標準保障額 = 企業防衛準備資金(社内留保) + 役員退職金慰労金準備資金(社外支出)という計算式になります。
企業防衛準備資金(社内留保)
- 企業防衛準備資金(社内留保)に該当するもの
- ➀運転資金(売上債権 + 棚卸資産 - 買入債務) × 必要倍数 + 固定費(人件費 + 固定経費) × 必要月数
- 中小企業において経営者はトップセールスを行っている場合が多いため、経営者に不測の事態があった場合、事業を後継者に承継した場合の売上の減少が予想されます。
当面の資金繰り(人件費・固定費)の悪化も考えられるのでそれに対する準備式資金が必要です。 - ➁借入金返済資金
- 本来事業を継承する場合、借入金の返済は直ぐには不要です。
ただ、中小企業においては「企業=経営者」という状況が考えられ、円満な取引維持のためには、金融機関等の対外信用力の維持が必要となります。
そのための準備資金です。 - ➂納税準備資金
- 運転資金や借入金返済資金として活用する保険金の収入は、社内留保分として会社の資産となるため課税対象となります。
従って、運転資金や借入金返済資金に保険金を全額活用する場合は、納税資金を準備しなければなりません。
運転資金や借入金返済資金を十分活用できるよう同時に準備しておくべき資金です。
経営者の信用と手腕で成り立っている中小企業の多くは、経営者の死亡、就業障がいおよび重大疾病時に次のような事態が想定されます。
- 売上減少による収益の悪化
- 固定費負担の深刻化(家賃やリース料の負担等)
- 給与支払の遅延による従業員の士気低下
- 従業員の退職金財源確保
- 金融機関からの信用力低下
- 金利や手形取引条件の厳格化、新規取引の停止
- 担保の追加提供
- 担保提供している自宅の差押
これらに備えるのが企業防衛準備資金となります。
役員退職金慰労金準備資金(社外支出)
- 役員退職金慰労金準備資金(社外支出)に該当するもの
- ➀役員退職慰労金(報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率)
- 本人もしくはご家族の生活費や相続税納税資金の財源となる資金です。
功績倍率参考例(注1):会長2.8 社長3.2 専務2.6 常務2.3 取締役2.0 監査役2.0 - ➁功労加算金(役員退職慰労金×0~30%)
- 会社発展にとくに功労があった場合に加算できる金額です。
- ➂弔慰金(報酬月額 × 6ヶ月(業務外)または36ヶ月(業務上))
- 死亡退職金と別科目で支給することにより、遺族が非課税で受け取ることができます。
業務外死亡の場合は報酬月額の6ヶ月、業務上死亡の場合は36ヶ月分が支給可能です。
注1
あくまでも参考例です。
資本金、従業員数、職種などの要因により異なります。
本人もしくはご家族の生活や相続を考えた場合、死亡退職金・弔慰金の支給は重要です。
また、事前準備(財源の確保)をしていないと、後継者に次のような負担をかけることになります。
- 借入や不動産の売却で資金を捻出すると・・
- 突然の社長交代で売上ダウンが予想されるなか、事業目的以外の借入や資産の減少は、後継者に厳しい経営上の負担を残すこととなります。
- 不動産が希望どおりの金額で売却できるとは限らないため、多額の売却損が発生した場合は、赤字が膨らむことにもなりかねません。
- 預貯金を取り崩すと・・
- キャッシュフローが悪化し、経営に悪影響を及ぼしかねません。
- 死亡退職金の支給財源を預貯金で確保するには、相当長い準備期間が必要となります。
- 退職金の支給ができない・・
- 本人もしくはご家族が従来どおりの生活を維持することが困難になり、ライフプランの変更を余儀なくされます。
- 換金性に乏しい自宅・土地・自社株などを相続した場合、死亡退職金(=現金)がないと相続税の支払いが困難となります。
これらに備えるのが役員退職金慰労金準備資金となります。
標準保障額の算定例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ➀運転資金 + 固定費 (運転資金 × 必要倍数 + 固定費(月額) × 必要月数) | 1,818万円 (480万円 × 1.0倍 + 223万円 × 6ヶ月) |
| ➁借入金返済資金 (借入金残高 × 必要返済割合) | 1,492万円 (1,492万円 × 100%) |
| ➂その他の負債 | 0万円 |
| ➃現金化可能な資産 | ▲508万円 |
| ➄納税準備資金 (法人税等実行税率33.58%の場合) | 1,416万円(注1) |
| A.企業防衛準備資金(社内留保) (➀~➄の合計) | 4,218万円 |
| ➅役員退職慰労金 (報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率) | 2,048万円 (40万円 × 16年 × 3.2倍) |
| ➆功労加算金 (役員退職慰労金 × 0~30%) | 614万円 (2,048万円 × 30%) |
| ➇弔慰金 (報酬月額 × 6 または36ヶ月) | 240万円 (40万円 × 6ヶ月) |
| B.役員退職金慰労金準備資金(社外支出) (➅~➇の合計) | 2,902万円 |
| 標準保障額【A + B】 | 7,120万円 |
注1
(➀ + ➁ + ➂ - ➃) / (1 - 法人税等実行税率) - (➀ + ➁ + ➂ - ➃)
2,802万円 / (1 - 33.58%) - 2,802万円 = 1,416万円
